ESマガジン一覧COLUMN
相続税計算の元となる「路線価」について解説
2021年10月8日
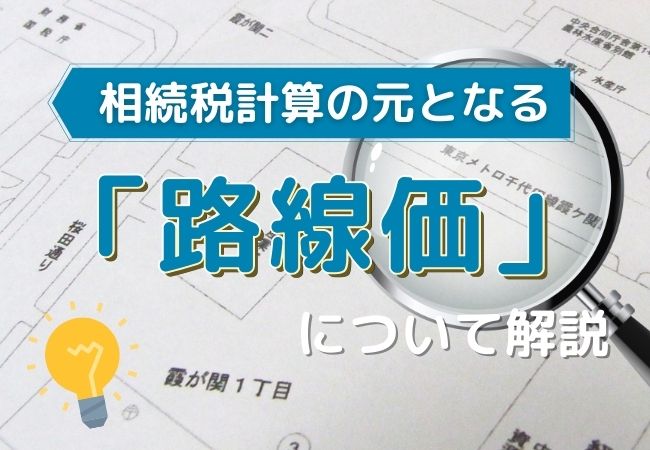
こんにちは!
皆さん「路線価(ろせんか)」という言葉を聞いたことはありますか?路線価とは、道路に面した土地の価格のことを言い、相続した財産の価値を評価する際に基準となる価格のことです。言い換えると、土地を譲り受けた時にどのくらい相続税・贈与税がかかるかは、路線価をもとに計算します。
今回は、そんな「路線価」について簡単に解説します。
路線価とは
路線価は、道路に面した土地の価格のことを言い、相続した財産の価値を評価する際に基準となる価格のことです。この路線価に応じて評価された額を基準に、相続税を支払います。相続される方にとっては重要なキーワードです。
路線価には2種類あり、それぞれ「相続税路線価」 、「固定資産税路線価」と呼ばれています。2種類について簡単にまとめました。
相続税路線価とは
相続税・贈与税の計算で使われる路線価
相続税路線価は、土地の相続税や贈与税を算出する際に基準にする評価額のこと。一般的には、「路線価」というと「相続税路線価」を差すことが多いです。国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1月1日を評価時点として3月に公示する公示地価の8割程度を目処に設定。そして、国税庁(税務署)により、毎年1月1日時点の価格が7月初旬頃に公表されています。
固定資産税路線価とは
固定資産税の計算で使われる路線価
固定資産税路線価は、市町村長(東京都区部では東京都知事)が固定資産税を課税するにあたり、定めるものです。宅地を評価するために道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価格のことをいいます。このように、固定資産税路線価は、道路に対して評価される価格で、1㎡あたりの単価です。
国土交通省が公示する地価公示価格の7割を目処にした価格を設定。
路線価はどうやって調べるのか?
路線価は、毎年7月1日に国税局や各地税務署で発表されます。
相続や贈与により土地の評価額を計算するときは、相続や贈与が発生した年の路線価を使います。

相続税路線価を使ってどのように計算するのか?
指定した地域の地図を見ると道路に「200E」などの表示があり、数字の部分が路線価になります。
数字を1,000倍したものが路線価であり「200」の場合は道路に20万円の路線価が設定されています。
この道路に面している土地は1㎡あたりの価格が20万円という考え方であり、相続の際には以下の計算で相続税評価額を算出します。
• 土地の相続税評価額:路線価×土地面積
路線価が200(20万円)、土地面積300㎡の場合、相続税評価額は以下のようになります。
• 土地の相続税評価額:20万円×300㎡=6,000万円
詳しくは、弊社へお気軽にご相談ください。

最後に
相続した不動産の売却は、一生の間に何でも経験することではありません。ほとんどの人が、疑問や不安を抱くものです。
「マイホームを建てたいから土地を探そう」という場合にも、土地の広さや立地、販売価格にばかり目が行きがちですが、後々のことまで考えるなら、路線価もきちんと踏まえて判断材料の一つにすることをお薦めします。
アースシグナルでは、相続された不動産でお困りのお客様に誠心誠意丁寧にサポートをしております。相続税についてお悩みの方、それ以外の不動産に関するお悩みもお気軽にご相談ください。