ESマガジン一覧COLUMN
土地を売りたい人必見! 土地の「価格基準」とは?
2022年3月24日
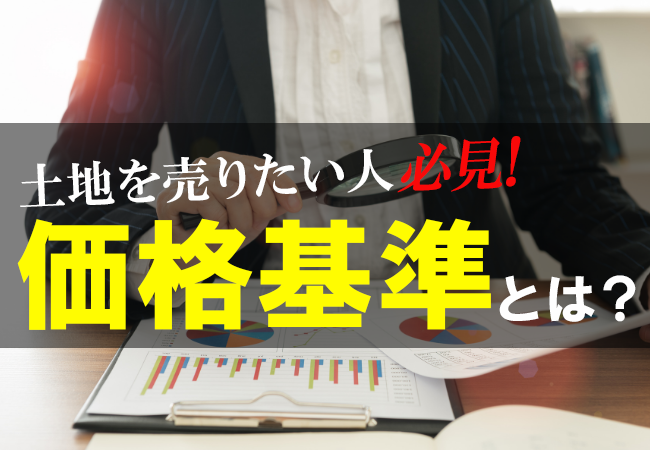
こんにちは!
今回のコラムは土地の価格基準についてご案内していきます。
まず土地の価格は5種類の基準となる価格があり、不動産会社ではその中のいくつかの価格を参考に、査定価格を考えております。
今回はそれぞれの基準の概要をご紹介します。
土地価格の基準
公示価格
公示価格とは「国土交通省」が毎年1月1日時点におけるその正常価格を複数の不動産鑑定士によって鑑定・審査をし、決定した価格です。
同年3月下旬に公表されます。
毎年テレビ番組やニュースで「地価が日本一高い地域は…」などと流れる場合の元になるのが公示価格です。
※主に「公共事業のための用地売買価格」に使われております。

基準価格
基準価格とは、公示価格に似ておりますが「都道府県」が独自に調査したものであり、7月1日時点における価格です。
同年の9月下旬に公表されます。
※主に「地方公共団体や民間企業の土地取引の目安」として活用されております。
実勢価格
実勢価格とは、実際の取引が成立する価格で「時価」とも呼ばれます。
実際に売買が行われた場合はその取引金額が実勢価格となり、取引がない場合は周辺の取引事例や他基準価格を参考に推測します。
※主に多くの「不動産会社が査定をする際」に使用いたします。
相続税路線価価格
相続税路線価とは、一般的に「路線価」と呼ばれる事もあります。
路線価は「国税庁」に毎年1月1日を判定の基準日とし、同年7月1日に公表されます。
目安として、公示価格の80%相当が評価水準となっており、実勢価格よりも低く設定される事が多いです。
※主に「相続税や贈与税の算定」に使われます。

固定資産税路線価価格
固定資産税路線価とは、各市町村が3年に1度その年の1月1日を基準に価格を更新しており、同年の4月頃に公表されます。
目安として公示価格の70%相当が評価水準となっております。
※主に「固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算定」に使われるものです。
| 項目 | 公示価格 | 基準価格 | 実勢価格 | 相続税路線価 | 固定資産税路線価 |
| 用途 | 公共事業のための 用地売買 | 地方公共団体や 民間企業の土地取引 | 不動産査定 | 相続税や贈与税 | 固定資産税、都市計画税、 不動産取得税など |
| 主体 | 国土交通省 | 都道府県 | 取引事例 | 国税庁 | 市区町村 |
| 頻度 | 毎年 | 毎年 | 都度 | 毎年 | 3年に一度 |
| 起算日 | 1月1日 | 7月1日 | 都度 | 1月1日 | 基準年の1月1日 |
| 価格水準 | 複数の不動産鑑定士による鑑定・審査 | 1名以上の不動産鑑定士による鑑定・審査 | 実際の取引事例 | 公示価格の80%相当 | 公示価格の70%相当 |
まとめ
結論、上記の価格基準の中で不動産会社が主に使用するのは「実勢価格」と2種類の「路線価」です。
特に「路線価」はご自身でも国税庁や各市区長村で調べる事が出来る価格です。
路線価の詳細は他のコラムでご紹介しておりますので、そちらのコラムも是非ご覧下さい。
また、ご自身で調べるだけでなく、私共へご依頼頂ければ条件によっては即日ご回答する事も可能です。
是非、お気軽にお問い合わせください。